-
家の庭や会社敷地内の庭木が大きくなりすぎて、少しでも安く剪定や伐採ができる業者を探している
-
草が生えて困っているので、防草シートや砂利敷きなど、雑草が生えないようにしたい
-
空き家の庭がうっそうとしすぎて、剪定や草刈りなど庭全体の手入れを検討中
-
法人様管理物件や自社チェーン店舗の植栽や雑草管理を一元的に請け負ってくれる業者を探している

00,000件
00,000件
00,000件
まずは何社のお庭の達人(造園業者・庭師さん)がマッチングできるか簡単チェック!!


アナタにピッタリの
造園業者・庭師がすぐに
見つかる!
「お庭の達人」は地域のプロの造園業者や庭師さんと直接出会える新しいサービスです。
ご依頼内容を入力するだけで、最適な造園業者や庭師さんと即マッチング!
全国どこでも
すぐ見つかる!
実績や口コミも
豊富だから
安心して選べる!
お見積
無料!

業者登録数 日本最大級!
庭の手入れ系の悩み
造園系庭づくりの悩み
-
庭木の新規植栽や植替えに伴う移植など、少しでも安く造園工事ができる業者を探している
-
草が生えて困っているので、防草シートや砂利敷きなど、雑草対策を考えている
-
新規で天然芝の芝張りや、既存の芝生の張替えを検討中
-
土の入れ替えや、庭石の設置又は撤去、人工芝敷きなど部分的な造園工事を請け負ってくれる業者を探している
お庭の達人では個人法人問わず、庭や商業施設、空き家や駐車場など造園・ガーデニングに関するご希望のサービス内容に関して、最短3分でできる見積依頼シミュレーションをすることで、数多くの造園・ガーデニング業者から多くの提案が舞い込みます。
経験豊富なお庭の達人(造園・ガーデニング業者)に依頼して、あなたの要望をしっかり叶えてもらいましょう!生活関連サービス全般の比較サイトではなく、お庭専門の業者だけが登録しているサービスだから、より専門的知識と技術、もちろん提案力も非常にレベルの高い達人と多数出会えます。 簡単・無料・相見積もり大歓迎の造園・ガーデニングサービスは、お庭の達人で。
まずは何社のお庭の達人(造園業者・庭師さん)がマッチングできるか簡単チェック!!
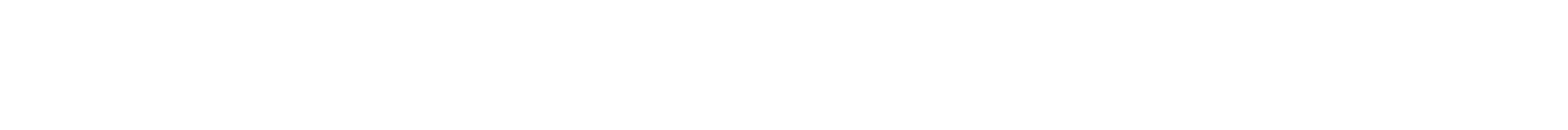
こんなお庭のお悩みありませんか?

お庭の仕事を頼もうと思っても、他の業者は忙しくて何週間もかかってしまう

派遣されてきた庭師さんがあまり良いお仕事をしてくれなかった経験がある

電話での説明や現地での調査など手間がかかるのが面倒…
お庭の達人ならすぐに、
見積&施工対応が可能!
依頼をかけると何十社からのオファーを受けて、
気に入ったお庭の登録業社とマッチング!
すぐに無料のお見積を取ることができます!

ご利用の流れ
ご依頼前に達人(業者)に直接質問
新築外構は作業時間で値段が変わりますか?気の大きさや太さなど量で変わりますか?
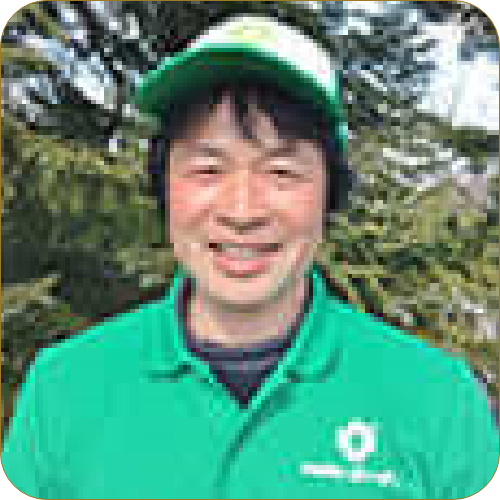
渡辺造園東京都葛飾区高砂

渡辺造園東京都葛飾区高砂
回答が入ります。回答が入ります。回答が入ります。回答が入ります。回答が入ります。回答が入ります。回答が入ります。回答が入ります。回答が入ります。

渡辺造園東京都葛飾区高砂
回答が入ります。回答が入ります。回答が入ります。回答が入ります。回答が入ります。回答が入ります。回答が入ります。回答が入ります。回答が入ります。
造園・ガーデニングの適期と可能時期

造園・ガーデニングサービスは大きく分けて2つあり、1つ目は造園系庭づくり、そして2つ目は造園系庭の手入れです。
造園系庭づくりの場合は、庭木植栽・生垣や植込み植栽・肥料・移植や植替え・天然芝の芝張り・土の入れ替え・防草シートや砂利敷き・人工芝・壁面緑化や屋上緑化などがあり、造園系庭の手入れは庭木の剪定や松の木の芽摘み、コニファーや生垣等の刈込、樹木への肥料、毛虫や害虫から守るための消毒、雪国には欠かせない樹木の枝折れから守る雪吊りや冬囲いなどがあります。
では、それらの適期や可能な時期は一体いつなのでしょうか?
気候は大きな要素となります。
植物を扱う以上、枯れてしまわないように誰もが適期に作業をしてほしいと思いますし、それによって依頼する時期も迷われる方も多いかと思います。
しかし、適期にこだわりすぎるデメリットも存在しますので、必ずしも適期に行うことがメリットばかりではなく、むしろ可能時期はいつなのかを覚えておきましょう。
ここでは、各作業別で適期や可能時期を紹介しながら、それに伴ってメリットやデメリットも一緒にご紹介いたします。
剪定とは?

剪定には手法として大きく分けて「強剪定」と「軽剪定」の2種類があります。
強剪定:新芽が出る前に枝や葉をカットし樹木の成長を促す剪定方法。骨格だけを残して多くの枝を切るため、木にとって負担が大きい剪定作業である。
軽剪定:軽く枝を透いたり切り詰めたりする剪定。見栄え良く樹木全体の形を整える剪定方法。日当たりを良くすることで害虫や蜂の巣づくりから予防できる。切り戻し剪定・透かし剪定などと言われる。
刈込剪定:刈込に耐えうる樹木に対して行う剪定手法。目隠しやフェンスの変わりに作る生垣や、マキやツゲなどの玉散らし(段作り)の庭木は基本的に刈込剪定を行う。
庭木の種類は主に「落葉広葉樹」「常緑広葉樹」「常緑針葉樹」が挙げられます。主な樹木は下記の通りです。
落葉広葉樹:ヤマボウシ、ウメ、ケヤキ、桜、アオダモ、モミジ、ハナミズキ、ジューンベリー
常緑広葉樹:椿、サザンカ、シマトネリコ、キンモクセイ、カシの木、クスノキ、ミモザ
常緑針葉樹:黒松、赤松、五葉松、スギ、ヒノキ、マキ、ゴールドクレスト、コニファー
庭木剪定の適期と可能時期について

植木や庭木は剪定することで形を整えることや、風通しを良くして虫の発生から木を守るためにも非常に大切なことです。しかし、枝を切るということは、少なからず庭木へダメージを与えることになります。
そのダメージを与える程度(切る量)や時期を考えて剪定しなければ、最悪枯れてしまうこともあるのです。
例えば、庭木を含む植物全般として、春から晩夏にかけて良く成長します。その成長期に大幅に樹形を変える剪定(強剪定)をすると、樹種によっては樹木への負担が非常に重く、枯れてしまう場合があったり、同じく常緑樹の場合は寒さに弱いため、冬眠期である真冬に切りすぎると枯れてしまう樹種もあったりします。
つまり、適期とは樹木全般一色単に同じ時期ではなく、樹種によって違うということを覚えておきましょう。
また、後述しますが、剪定する量が多い場合の強剪定には適期が重要ですが、芽を残して透かしたり切り詰めたりする軽剪定の場合は、適期にこだわる必要はありません。1年中可能です。
そのため、剪定の仕方別に下記にお伝えしますので、詳しく見ていきましょう。
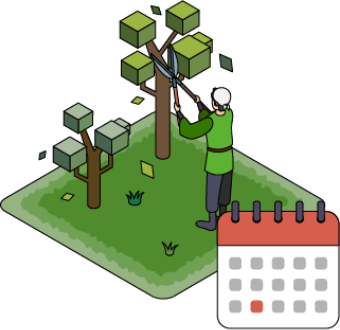
強剪定の適期と可能時期
樹形を気にせず木を半分に切る半伐採や、葉をほぼ残さずに骨格だけにする強剪定など、その適期と可能時期は一体いつなのでしょうか?
上述の通り、春から晩夏にかけて樹木は成長が活発で体力を良く使う時期になるため、その時期に強いダメージを与えるのは枯れてしまう可能性がある作業です。
そのため、樹形を変えてしまうような強めに切る強剪定の場合は、成長期以外での実施が重要です。ただし、寒さにも弱い常緑樹の場合は真冬以外での実施がおススメです。
なお、庭木の種類には、1年を通して葉がついている常緑樹と、季節によって葉が落ちる落葉樹があります。さらに葉の形状によって、葉が針のように細い針葉樹と、広く平らな広葉樹とに分かれます。それぞれの種類ごとに強剪定の適期と可能時期を次にまとめますので見ていきましょう。
| 強剪定・半伐採の 適期 |
強剪定・半伐採の 可能時期 |
適期の理由 | |
|---|---|---|---|
| 落葉樹 | 11月〜2月 | 10月〜3月 | 落葉中の冬は冬眠期であり、樹木の負担を少なくできるため。 |
| 常緑広葉樹 | 3月〜5月 | ①2月〜6月 ②9月〜11月 |
冬が終わり、活発に成長する前の初春が適期。なお、常緑樹は寒さに弱いため、成長しない冬も避けるぺき。 |
| 常緑針葉樹 | 3月〜4月 | ①2月〜5月 ②9月〜10月 |

軽剪定の適期と可能時期
うっそうと成長してしまった庭木を、樹形を良くするためや風通しを良くするための剪定を軽剪定と言います。
軽剪定は、切り詰めたり透かしたり、芽を残して剪定する方法で、技術力が問われる剪定です。
そんな軽剪定は強剪定と違ってそこまで木にダメージを与えませんし、むしろさっぱりさせることで成長を促進したり、毛虫から身を守るために非常に良いことです。
そのため、基本的にはいつ軽剪定しても大丈夫ですが、適期もあります。
庭木の種類ごとに見ていきましょう。
| 軽剪定(切り戻し剪定・ 透かし剪定)の適期 | 軽剪定(切り戻し剪定・ 透かし剪定)の可能時期 | 適期の理由 | |
|---|---|---|---|
| 落葉樹 | ①2月〜3月 ②6月 ③9月〜11月 |
1年中可能 | 落葉樹は真夏の勤定は強めのコ定を避ける。軽めに透かす軽勤定なら年中可能。 |
| 常緑広葉樹 | ①3月〜4月 ②6月〜11月 |
1年中可能 | 常緑樹は寒さに弱いため、冬の強めの第定を避ける。軽めに透かす軽薄定なら年中可能。 |
| 常緑針葉樹 | ①3月〜5月 ②7月〜11月 |
1年中可能 |

松の木剪定の適期と可能時期
松の木の代表種として黒松(クロマツ)、赤松(アカマツ)、五葉松(ゴヨウマツ)がありますが、どんな種類でも松の剪定は春と秋が適期です。
春の剪定は「みどり摘み」と言い、新芽を放置すると樹形が乱れてしまう原因になるので、春に新芽を除去して松の樹形を保つために行います。秋の剪定は「もみあげ」と言い、不要な葉や枝、枯れ葉を手で取ることで樹形を整え、その結果、日当たりや風通しが改善され病害虫からの被害を受けにくくなります。
つまり、松の剪定は年間2回行うことがベストです。
ただし、春や秋の剪定は適期ではありますが、基本的に松の剪定は強めに切ることはせず、ダメージの少ない透かし剪定などの軽剪定がメインとなりますので、年間を通して剪定が可能です。
最近では、費用の節約のため、年間に1回の剪定に留めることが多く、1度で「みどり摘み」と「透かし剪定やもみあげ」を行うことがほとんどとなっています。
| みどり摘みの適期 | 透かし剪定・もみあげの適期 | 剪定可能時期 | |
|---|---|---|---|
| 黒松(クロマツ) | 4月〜5月 | 10月〜12月 | 1年中可能 |
| 赤松(アカマツ) | 4月〜5月 | 10月〜12月 | 1年中可能 |
| 五葉末 | 4月〜5月 | 10月〜12月 | 1年中可能 |

適期に剪定するデメリット
庭木を適期に剪定するメリットがある一方、適期に剪定するデメリットもあります。例えばそれは、造園業者や庭師に依頼する場合です。
適期ということは、業界全体でどの業者も繁忙期のため、業者に依頼すると長期間待たされることや、繁忙期価格は無くとも、工事費用が割高になったり値引きは一切なかったりする場合があります。
そのため、庭木の剪定を業者に依頼する場合は、適期を多少外して依頼することが、安く剪定するコツです。
なお、適期を外した時期かつ、造園業者が比較的閑散期となる時期とは、1~3月です。
【補足】花を楽しむための剪定時期
庭木の多くは華やかな花を咲かせ、我々に四季を感じさせてくれます。そんな綺麗な花をたくさん咲かせるためには、剪定の時期に注意しなければなりません。
例えば、花が咲くためには、必ず数ヶ月前に花芽を付けてつぼみに変わります。その花芽やつぼみを切ってしまうと当然ですが花が咲かなくなるのです。
そのため、花芽が付く時期を見極め、剪定しなければなりません。
では、いつ花芽を付けるのでしょうか?樹木の種類は非常に多く、種類ごとに覚えていてはキリがありません。覚え方として、いつの時期に花が咲くのかで花芽を付ける時期を見極めることができますので、下記にまとめますのでご欄ください。
ただし、花芽の出来る枝や位置によっても変わる場合があるのでご注意ください。
| 春に花が咲く庭木 | 夏に花が咲く庭木 | 秋に花が咲く庭木 | 冬に花が咲く庭木 | |
|---|---|---|---|---|
| 花芽をつける時期 | 前の年の花が咲き終わった時期〜夏頃 | 直前の春 | 直前の春〜夏 | 直前の春〜夏 |
生垣・植込み刈込の適期と可能時期について

生垣や植込みは、最初に植えた際は目隠し度が薄くスカスカですが、数年かけて樹木を刈り込むことで葉の密度を高めることができ、目隠し度が高くなります。
決まった高さに保ちたいのであれば、毎年決まった箇所で刈り込むことが欠かせません。
そんな生垣の適期はいつなのでしょうか?
基本的に生垣は目隠し目的のため、年中葉が付いたままの常緑樹がメインですので、常緑樹の適期と同じとなります。
例えば、生垣でよく使われる樹木として下記があります。
常緑広葉樹・・・レッドロビン・トキワマンサク・サザンカ・ツバキ・シルバープリペット・シラカシ・ボウガシ
常緑針葉樹・・・カイヅカイブキ・コニファー・イヌマキ・ラカンマキ・イヌツゲ・キンメツゲ
ただし、刈込剪定でも強い剪定か弱い剪定かによっては時期が違うので注意が必要です。
| 生垣・植込みの強剪定 の適期 |
生垣・植込みの強剪定 の可能時期 |
生垣・植込みの刈込 の適期 |
生垣・植込みの刈込 の可能時期 |
注意点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 落葉樹 | 11月〜2月 | 10月〜3月 | ①2月〜3月 ②6月 ③9月〜11月 |
1年中可能 | 生垣の刈込は通常形を整えるために行う軽◎定です。そのため、基本的には庭木の勤定の時期と同じです。 ただし、生垣の花を楽しむために剪定する場合には、花の芽を付ける時期に注意し、刈り込む時期を見極めなければなりません。 |
| 常緑広葉樹 | 3月〜5月 | ①2月〜6月 ②9月〜11月 |
①3月〜4月 ②6月〜11月 |
1年中可能 | |
| 常緑針葉樹 | 3月〜4月 | ①2月〜5月 ②9月〜10月 |
①3月〜5月 ②7月〜11月 |
1年中可能 |
庭木への消毒の時期や頻度について

植物である以上、病気になったり毛虫や害虫には食べられてしまったり、最悪の場合、虫が木の幹の中に入って枯らしてしまうこともあります。
そんな毛虫や病気は我々人間が薬を飲むのと同じように予防や治すことができます。
大切な庭木が害虫や病気によって枯れてしまわないようにするためにも、庭木消毒はしっかりと行う必要があります。
しかし、庭木の消毒を行う際には、作業に適した時期や薬剤の種類はもちろん、さまざまな注意点などについて知っておかなければなりません。それらについて、ここではまとめます。
もちろん、生垣の消毒も植込みの消毒も同じです。

消毒の適期と回数
庭木への消毒は、基本的に年に3回行うのが望ましいのですが、その時期によって利用する薬剤やその散布の目的が変わります。
例えば、1~2月などの冬の時期に行う消毒は予防が目的です。なぜなら、冬には毛虫や害虫は冬眠期のため、活動をしていないからです。
他に、3~5月などの春には、毛虫や害虫が活発に活動を始め始める時期です。そのため、被害を最小限に抑えるための消毒を行います。
暑い時期である6~9月には、毛虫や害虫が最も活発になる時期です。アオムシやイラガなどに葉が食い尽くされたり、カミキリムシなどが子供を産むために幹の中に入る準備を行う時期でもあります。
こまめに消毒をおこない、庭木への被害を最小限に抑えることが大切です。
通常、庭師さんに依頼すると、庭木に合わせて殺虫剤と殺菌剤、展着剤を混ぜて消毒してくれます。
| 目的 | 起こりやすい被害 | |
|---|---|---|
| 春の消毒 | 殺虫・殺菌 | 食害・病気 |
| 夏の消毒 | 殺虫・殺菌 | 食害・枯れ・病気 |
| 秋の消毒 | 必要なし | 病気 |
| 冬の消毒 | 予防 | − |

庭木の消毒に使用する薬剤の種類
庭木の消毒といっても、農薬にはさまざまな種類が存在します。毛虫や病気の種類に応じて農薬を選ばなければなりませんが、これは地域により出現する虫が変わってくるため、地域によっても使用する農薬を変えていく必要があります。
つまり、消毒する目的によって適切な薬剤を選ぶ必要があります。薬剤の種類は以下のとおりです。
なお、農薬のため非常に危険です。必ず希釈濃度を守ってご使用ください。
また、消毒が効く期間を長く持たせるためのコツとして、展着剤を農薬と混ぜて使用するとより効果が長持ちします。
| 殺虫剤 | 殺虫剤は、すでに庭木に発生している毛虫や害虫を駆除するのに利用する薬剤です。葉を食べられるなどの被害を防ぐために有効です。 主にスミチオン・オルトラン・マラソン・カルホス・マツグリーンがあります。 |
|---|---|
| 殺菌剤 | 害虫や菌が付くことから予防し、病気を防いだり治療したりする効果がある薬剤です。害虫を駆除しつつ、再発生や病気の予防もできるまさにワクチンとしての薬剤といえます。 主にトップジン・オーソサイド・ダコニールがあります。 |
草刈り・除草・除草剤の時期や頻度について

雑草魂という言葉からも、雑草は非常に強力な生命力を持つ植物です。
雑草も光合成をするため、地球にとって無くてはならない存在ではありますが、人間にとったら非常に手間で煩わしいもの。
しかし、草刈りや草むしりなどをしないと、大切にしている庭木や芝生、お花など、他の植物を枯らしてしまったり、防犯的にも印象が悪かったり、蜂や害虫が巣を作ってしまうことさえあります。
そのため、人の手による雑草の管理は色々な面で非常に大切です。
では、そんな雑草の草刈りや草むしりはどの頻度でいつの時期に行うのが良いのでしょうか?
近所の印象や、来られる方への見た目を気にすることがある家の庭の場合や、商業施設、空き家や管理している空き地(農地や遊休地)、貸している駐車場の場合とではメンテナンスの頻度が違うかもしれません。
そこで、見た目も印象も悪くなりにくい最低限の回数という視点で、頻度や時期を下記の表にまとめますので参考にしてください。
| 最低限の 除草頻度 |
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 理由や注意点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 住んでいる 家の庭 |
年間4回 | 10月〜3月 | 10月〜3月 | 9月〜10月 | 11月〜12月 | ご自宅の場合は、この頻度と時期に行うことで、草が生える密度を低く、草が伸びても草丈50cm以内で管理することができます。 |
| 商業施設・ 貸駐車場 |
年間3回 | 5月〜6月 | 8月〜9月 | 11月〜12月 | − | 印象やイメージを大切にする商業施設や駐車場の場合でも、企業は雑草の管理に余り予算が掛けられません。年間4回が望ましいですが、最低でもこの頻度と時期に行うことで、草が生える密度は多少高いですが、伸びても草丈100cm以内で管理することができます。 |
| 空き家・ 空き地 |
年間2回 | 6月〜7月 | 10月〜11月 | − | − | 草丈が100cm以上になると防犯的に印象が悪く、しかも蜂や害虫が巣を作りやすい環境になるのですが、それを最低限防ぐためには本来は年間3回の草刈りが必要です。しかし、普段使用しない箇所に予算を余り掛けられないかと思いますので最低限年間2回は行いたいところです。年間1回ですと、知らず知らずのうちに近所の迷惑となっています。 |
草刈りと草むしり ―それぞれのメリット・デメリット―
雑草を処理する方法として代表的な方法が、機械を使った草刈りと、誰もがやったことがあるであろう人の手で直接抜く草むしりです。
草刈りは、草が生えている面積が広範囲の場合に行うことが多く、草むしりは草が生えている場所が狭い場所や、構造物や配線などがあって機械で行うと危険な場所、植込みなどの木の間に生えている草を取る際に行うことが一般的です。
草刈りの場合、肩掛け式の機械よりさらに効率の良い手押し式のロータリーモア草刈り機、さらに強力な草刈り機であるハンマーナイフで行うことができる場合は、より効率よく草を刈ることができます。
業者に依頼する場合、効率が悪い方法であればあるほど費用がかさんでしまうため、効率の良い機械(重機)でできる業者に依頼することで、単価を安く依頼することができるでしょう。
なお、草むしり自体は簡単な作業ではありますが、草むしりを業者に依頼する場合、プロの業者であろうと非常に時間がかかって効率が悪い作業となるため、思いのほか見積は高くなりがちです。
| 可能な草丈 | 草の根の残りレベル | 作業の手間・スピード | メリット | デメリット | |
|---|---|---|---|---|---|
| 草刈り (肩掛け式草刈り機) |
草丈に関わらず可能 | 生え際で刈るため完全に根は残る | 草丈や作業環境によるが1日で200~600㎡程度刈ることができる | ・面積に対して効率が良いため比較的安価に刈ることができる | ・再度生えるまでの期間が短い(夏だと2週間で結構伸びる) |
| 草刈り (ハンマーナイフなどの重機) |
草丈1.5m程度 | 生え際で刈るため完全に根は残る | 重機などのハンマーナイフ等であれば、効率良く1日でかなり広い面積を刈ることができる | ・面積に対してかなり効率が良いためかなり安価に刈ることができる | ・再度生えるまでの期間が短い(夏だと2週間で結構伸びる) ・機動力が悪いため狭い場所だと反対に高くなる |
| 草むしり (手抜き除草) |
現実的に草丈100cm程まで | ある程度の根は抜けるが先端の方は切れてしまうため完全には抜けない | 手で抜くため効率が悪く時間がかかる | ・根まである程度抜けるため、生えない持続期間が長い | ・効率が悪い作業のため面積の割には手間と費用がよりかかる |
除草剤のタイプとそのメリット・デメリット
草に農薬を散布することで枯らすことができる除草剤。
除草剤といっても、粒状のものや液体の物など様々な種類が存在します。なぜなら、今生えている草に対してなのか、予防に対してなのかなど、生えている雑草の状態に応じて使用する除草剤が変わるためです。
枯らしたい植物や状況に応じて、適切な除草剤を選択しましょう。
基本的に粒剤タイプは、「土壌に浸透させて草の根を隅々まで枯らす」目的で行います。そのため、今生えている草はもちろん、今はまだ地上に姿を現していない草の根まで枯らします。
そのため、持続性が高い方法です。ただし、効果が出るまでに1週間ほどかかるでしょう。
反対に液体タイプは、「今生えている草を枯らす」目的で行います。効果が出るのは数日ですが、地上に表れていない草の根は枯らすことはできませんので、また別の草が生え、持続性はありません。
それぞれのメリット・デメリットを下記に表します。
| 用途・目的 | 効果がある草丈 | 効果出るまでの時間 | 効果の持続性 | メリット | デメリット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 粒状タイプ | ・雑草を長い期間生やしたくない | 草丈30cm程まで | 1週間程度 | 3~6ヶ月ほど(時期による) | ①草刈り後に行えば、草があまり生えない期間が持続する | ①広い面積の場合はかなりの量がいるため費用が高い ②隣地の土壌まで浸透する場合があり危険 |
| 液体タイプ | ・雑草を即効で枯らしたい | 草丈100cm程まで | 即日~数日 | 持続性はなし(現在生えている草のみ枯らす) | ①少ない量で広い面積に散布可能 ②隣地に庭木や畑がある場合、直接かけてしまうことを除き、土から浸透して枯らしてしまうことはない |
①またすぐに新しい草が生えてくるため、年間の手間が多くかかる |
除草剤の種類
除草剤のタイプ別のメリットやデメリットが分かったところで、それぞれ代表的な除草剤をご紹介いたします。
DIYする場合は、農薬で非常に危険ですので必ず使用注意点を読んで正しくお使いください。
最近では、芝生は枯らさず雑草だけ枯らすタイプのものまで販売されています。
| タイプ | 農薬登録 | 適用雑草 | |
|---|---|---|---|
| ラウンドアップマックスロード (日産化学) |
液体タイプ | ○ | ・1年生雑草 ・多年生雑草 ・スギナ |
| サンフーロン (大成農材) |
液体タイプ | ○ | ・1年生雑草 ・多年生雑草 ・ススキ ・ササ |
| グリホエースPRO (ハート) |
液体タイプ | ○ | ・1年生雑草 ・多年生雑草 ・スギナ ・ササ ・つる草 |
| ネコソギエースV (レインボー薬品) |
粒剤タイプ | ○ | ・1年生雑草 ・多年生雑草 ・スギナ |
| ネコソギトップW (レインボー薬品) |
粒剤タイプ | ○ | ・1年生雑草 ・多年生雑草 ・ススキ ・ササ |
除草剤の注意点
除草剤の散布は必ず使用注意点を必ず守り、用法・容量を厳守することが重要ですが、他にどんな注意点があるのかをご紹介します。
①傾斜地や川・田んぼの近くでは使用しない。
②近くに樹木がある場合は使用しない。
③除草剤散布時はマスクや保護メガネを着用し、散布後は手洗い、うがいをし、着用着は洗濯する。
正しい方法で、正しい知識をもって使用しないと、他人の所有物である樹木を枯らしてしまったり、田んぼや川に除草剤が流れて農作物を全滅させるという事故も起きています。
そうなってしまうと、多額の賠償費用を払わなければならない場合があります。不安であれば、ぜひプロの庭師にご依頼ください。
芝刈り・エアレーション・目土の時期や頻度について

天然の芝生を綺麗に保つためには、人の手による管理が欠かせません。
芝刈りは当然として、暑い時期には水やりを、硬くなった土壌には、専用器具で穴をあけて根の通気性を良くするためのエアレーション作業を、その空けた穴に新しい土や肥料を入れて根を張れるようにするための目土作業や施肥作業が必要です。
そんな多種多様な芝生のメンテナンス作業はいつの時期に、最低限どのような頻度で行えばよいのか下記表にまとめてご紹介いたします。
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | |
|---|---|---|---|---|
| 芝刈り | 4~5月 | 6~7月 | 8~9月 | 10~11月 |
| エアレーション | 4~5月 | ― | ― | ― |
| 目土 | 4~5月 | ― | ― | ― |
| 肥料 | 4~5月 | ― | ― | ― |
1.庭木植栽(生垣・植込み含む)の適期と可能時期について

植木や庭木を購入する際、園芸屋さんや植木屋さんで販売されている植木を購入することがほとんどだと思いますが、お客様のお庭に新たに植わる植木は、出荷するために植木屋さんの畑や農場で育てられた植木の根を切って出荷されます。
庭木などの植物全般は土中の水分を根から吸収しますが、出荷のためにせっかく張った根を切り取られるため、庭木が成長するのに非常に重要な水分を吸収する能力が一時的にダウンする状態となります。
一方で、植物は葉から水を蒸散したり、光合成のために水が使用されて酸素を排出しますが、蒸散は人間で言う汗と同じように暑い夏の時期により活発になります。なぜなら、汗も蒸散も体温調節のために行われる現象だからです。
つまり、庭木など植物全般も人間と同じように水分が命の源ですので、出荷のために起こる水分吸収能力下落が、蒸散や光合成が活発な暑い時期に当たると、水分が足らずに枯れる可能性が高くなるのです。
このことから、新たに庭木を植栽する場合は、基本的に暑い時期を避けるようにしましょう。
地域にもよりますが、基本的に関東以南では6月・7月・8月を避け、関東以北では7月・8月を避けることが、植栽のコツの一つです。

庭木植栽(生垣・植込み含む)の適期とそのメリット
植栽のダメな時期は分かりましたが適期は一体いつで、その効果やメリットは何なのでしょうか?
上述の通り、暑い夏の時期に蒸散や光合成が活発になるため、いかに夏に向けて水分を吸収できる能力を高めるかが元気に育つ鍵となります。
つまり、夏までに少しでも根を長く広く伸ばさせることが最も最適な植え方のため、夏に遠い時期が最適な適期となります。
では冬はどうかと言うと、多くの植物は冬の間は休眠期となるため、冬の間はあまり水を必要としませんので一見適期かと思うかもしれませんが、冬に植えてしまうと、そもそも出荷のために根を切られて弱っている状態の木では、寒さに耐えられずに枯れてしまうこともあります。(ただし、夏の植栽に比べて冬の植栽はそこまで深刻ではありません)
そのため、秋~冬も同じように、冬を迎える休眠期前に根を少しでも成長させたいとなります。
つまり、庭木の植栽で最も良い適期は、春の植物が動き出す前から桜の花が咲くころの2~4月と、寒い冬を迎える前でまだ植物が休眠期に入っておらず成長する9~10月となります。
ただし、常緑樹か落葉樹かによっても多少違うため、下記に庭木の種類別にまとめますので参考にしてください。
| 庭木の植栽の適期 (生垣・植込み含む) |
適期の理由 | 適期に行う効果やメリット | |
|---|---|---|---|
| 落葉広葉樹 | ①1~4月 ②9~10月 |
植物にダメージを与える夏や冬を迎える前に少しでも根を成長させることができる時期のため。 | 根を適切に活着させることができ、枯れにくくなる。 |
| 常緑広葉樹 | ①2~5月 ②9~10月 |
||
| 針葉樹 | ①2~4月 ②9~11月 |

適期に植えるデメリット
庭木を適期に植えるメリットがある一方、適期に植えるデメリットもあります。例えばそれは、造園業者や庭師に依頼する場合です。
適期ということは、業界全体でどの業者も繁忙期のため、業者に依頼すると長期間待たされることや、繁忙期価格は無くとも、工事費用が割高になったり値引きは一切なかったりする場合があります。
そのため、庭木の植栽を業者に依頼する場合は、適期を多少外して依頼することが、安く植栽するコツです。
なお、適期を外した時期かつ、造園業者が比較的閑散期となる時期とは、1~2月です。

庭木植栽(生垣・植込み含む)の可能時期
上述の通り、適期というのはありますが、基本的に真夏の7月、8月を避ければ、庭木の植栽や生垣、植込みの植栽はいつでも可能です。
なぜなら、枯れるか枯れないかの要素は、時期だけでなく植える場所の土の質や雨水の排水能力、そして植え方やその後の水やりなどのメンテナンスの方が大きく占めるからです。
そのため心配な方は、造園業者や庭師さんに現場を見てもらって土壌の質や排水性等を確認してもらいましょう。
例え水はけの悪い土壌であっても、根腐れを起こさないような植え方も存在します。
ここでは、適期ではなく可能時期を下記にまとめます。
| 庭木の植栽の可能時期 (生垣・植込み含む) |
可能時期の理由 | |
|---|---|---|
| 落葉広葉樹 | 7月・8月を除きいつでも良い | 水不足に陥りがちな真夏以外であれば植栽可能 |
| 常緑広葉樹 | 7月・8月・12月・1月を除きいつでも良い | |
| 針葉樹 | 7月・8月を除きいつでも良い |
2.植替えや移植の適期と可能時期について

樹木の移植・庭木の植え替えは、造園工事の中でも最も難易度が高い作業です。
なぜなら、何年も同じ場所に植わっていた樹木は基本的に枝張りと同じ分だけ地中で広く太く根を張っており、生かしたまま移植するには、適切な分量の根を残して切断し、移植しなければなりません。移植は技術力の高い造園業者でなければできない作業です。
そんな移植ですが、移植や植替えの時期は、植木屋さんで購入した庭木を新規で植えるより、よりシビアです。
なぜなら、上述の通り、庭木を移動(移植)するためには根を切らなければなりません。
命の源である水分を吸収する大事な大事な根を切ってしまうと、庭木が成長するのに重要な水分を吸収する能力が一時的にダウンする状態となります。
しかし、植木屋さんで販売されている植木は、水分吸収能力が低下すること前提に作られています。
つまり、根回しがされています。
※根回しとは、根を切った箇所から細かい根(細根と言う)が発生することを促す作業です。細根が多く出ているため、比較的水不足で枯れにくくなります。
一方で、同じ箇所に長年植わっている庭木の移植の場合は当然根回しがされていないため、切った箇所に細根はありません。つまり、新規の植栽より水不足で枯れやすい状態ということです。
このことから、移植する場合は基本的に時期に気を付けましょう。新規の植栽の場合は適期≠可能時期ですが、移植や植替えの場合は、適期=可能時期です。
可能時期以外にどうしても行う必要がある場合は、枯れる可能性が高いということを理解して、造園業者に依頼しましょう。
もし、期間に余裕があるのであれば、最低でも半年前に造園業者に根回し作業を依頼しましょう。
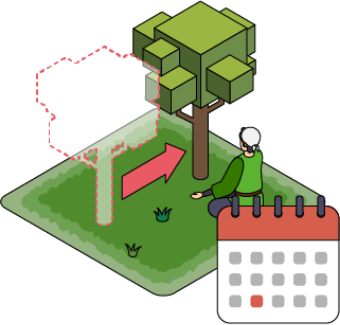
植替えや移植の適期とそのメリット
植替えや移植の適期=可能時期は分かりましたが、その理由や適期に行うメリットは何なのでしょうか?
樹木は暑い夏の時期に蒸散や光合成が活発になるため、いかに夏に向けて水分を吸収できる能力を高めるかが元気に育つ鍵となります。
つまり、夏までに少しでも根を長く広く伸ばさせることが最も最適な植替えや移植のため、夏に遠い時期が最適な適期となります。
そのため、落葉樹の移植や植替えは落葉期から休眠期(10~3月)に、常緑樹の移植や植替えは少し暖かくなった3月ごろから新芽の出る前の4月と、新芽の止まる時期の6月、秋は9月~10月です。
色々なホームページで適期について様々書かれていますが、ホームページによって書いてあることが違い、困ってしまいますよね。
ですので、基本的にこれだけは覚えておきましょう。
なお、上記で述べた通り、常緑樹か落葉樹かによって時期が違うため、下記に庭木の種類別にまとめますので参考にしてください。
| 庭木の移植や植替えの適期 | 適期の理由 | 適期に行う効果やメリット | |
|---|---|---|---|
| 落葉広葉樹 | ①10~3月 | 休眠期のため | 根を適切に活着させることができ、枯れにくくなる。 |
| 常緑広葉樹 | ①3~4月 ②6月 ③9~10月 |
発芽前もしくは、新芽が止まる時期のため | |
| 針葉樹 | ①9~12月 ②3~4月 |
寒さに強く環境の変化に強いため |
3.天然芝の芝張り適期と可能時期について

庭木の植栽と同じく、天然芝も農場で生産されますが、出荷するためには育てられた芝生の根を切って出荷されます。
天然芝含め植物全般は土中の水分を根から吸収して成長しますが、出荷のためにせっかく張った根を切り取られるため、芝生が生きるために必須な水分を吸収する能力が一時的にダウンする状態となります。
一方で、芝生含む植物は葉から水を蒸散したり、光合成のために水が使用されて酸素を排出しますが、蒸散は人間で言う汗と同じように暑い夏の時期により活発になります。なぜなら、汗も蒸散も体温調節のために行われる現象だからです。
つまり、天然芝など植物全般も人間と同じように水分が命の源ですので、出荷のために起こる水分吸収能力下落が、蒸散や光合成が活発な暑い時期に当たると、水分が足らずに枯れる可能性が高くなるのです。
このことから、天然の芝生を張る場合は、基本的に暑い時期を避けるようにしましょう。
地域にもよりますが、関東以南では6月・7月・8月を避け、関東以北では7月・8月を避けることが、天然芝の芝張りのコツの一つです。
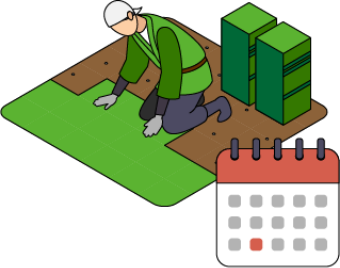
天然芝の芝張り適期とそのメリット
天然芝の芝張りのダメな時期は分かりましたが適期は一体いつで、その効果やメリットは何なのでしょうか?
上述の通り、暑い夏の時期に蒸散や光合成が活発になるため、いかに夏に向けて水分を吸収できる能力を高めるかが元気に育つ鍵となります。
つまり、夏までに少しでも根を長く広く伸ばさせることが最も最適な天然芝の張り方のため、夏に遠い時期が最適な適期となります。
では冬はどうかと言うと、西洋芝・日本芝と違いますが、基本的に天然芝は冬の間は休眠期となるため、冬の間はあまり水を必要としません。そのため、一見適期かと思うかもしれませんが、冬に張ってしまうと、そもそも出荷のために根を切られて弱っている状態の芝生では、寒さに耐えられずに枯れてしまうこともあります。(ただし、夏の芝張りに比べて冬の芝張りはそこまで深刻ではありません)
そのため、秋~冬も同じように、冬の休眠期を迎える前に根を少しでも成長させたいとなります。
つまり、天然芝の芝張りで最も良い適期は、春の植物が動き出す前から桜の花が咲くころの2~4月と、寒い冬を迎える前でまだ植物が休眠期に入っておらず成長する9~10月となります。
なお、下記に芝生の種類別にまとめますので参考にしてください。ただし、地域によって多少違うため、注意が必要です。
| 芝張りの適期 (種まき含む) |
適期の理由 | 適期に行う効果やメリット | |
|---|---|---|---|
| 日本芝 (高麗芝・TM9・野芝など) |
①3~6月 ②9~11月 |
植物にダメージを与える夏や冬を迎える前に少しでも根を成長させることができる時期のため。 | 根を適切に活着させることができ、枯れにくくなる。 |
| 暖地型西洋芝 (ティフトンなどバミューダグラス類) |
|||
| 寒地型西洋芝 (ベントグラス類、ブルーグラス類、フェスク類) |
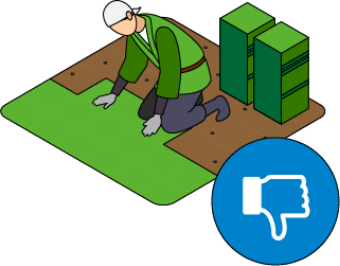
適期に芝を張るデメリット
天然芝の芝張りを適期に行うメリットがある一方、適期に芝張りを行うデメリットもあります。例えばそれは、造園業者や庭師に依頼する場合です。
適期ということは、業界としてどの業者も繁忙期のため、業者に依頼すると長期間待たされることや、繁忙期価格は無くとも、工事費用が割高になったり値引きは一切なかったりする場合があります。
そのため、天然芝の芝張りを業者に依頼する場合は、適期を多少外して依頼することが、安く施工するコツです。
ただし、雑草が生えてきてしまうとそれの処理が別で発生することもあるため、検討する時期によっては早めに行ったほうがいい場合もあります。
なお、適期を外した時期かつ、造園業者が比較的閑散期となる時期は、1~2月です。
DIYで行う場合は、小売屋さんで購入する必要があるかと思いますが、小売店さんではそもそも適期にしか芝生が販売されていませんのでご注意ください。
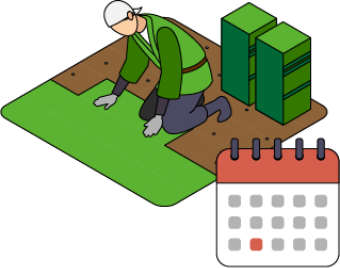
天然芝の芝張り可能時期
上述の通り、適期というのはありますが、基本的に真夏の7月、8月を避ければ、天然芝の芝張りはいつでも可能です。
なぜなら、枯れるか枯れないかの要素は、時期も大きな要素ですが、芝を張る場所の地面の土の質を良くすることや、雨水の排水能力、そして張り方やその後の水やりなどのメンテナンスも重要な要素だからです。
そのため心配な方は、造園業者や庭師さんに現場を見てもらって土壌の質や排水性等を確認してもらい、水たまりができたりする場合は、排水が悪く根腐れの元ですので、新たに綺麗な砂を地面に整地して水が流れるように勾配を付けて施工しましょう。
なお、地盤づくりはDIYでは難しいと思いますので、業者に依頼したほうが無難です。
| 芝張りの適期 (種まき含む) |
可能時期の理由 | |
|---|---|---|
| 日本芝 (高麗芝・TM9・野芝など) |
真夏の7月・8月と冬の始まりの12月を除きいつでも良い | 水不足に陥りがちな真夏以外であれば芝張り可能 |
| 暖地型西洋芝 (ティフトンなどバミューダグラス類) |
||
| 寒地型西洋芝 (ベントグラス類、ブルーグラス類、フェスク類) |
造園・ガーデニング業者の4つの選び方

造園・ガーデニング業者は地域によって数十社、数百社と存在します。
しかし、いったいどこの造園・ガーデニング業者に依頼すれば最善なのか、不安はありませんか?
高い費用を出して造園・ガーデニングを依頼する以上、誰もが失敗したくないのは当然のことです。
だからこそ、様々な造園・ガーデニング業者に相見積もりを取って、是非ベストな提案を選んでください!
お庭の達人では、プロの造園・ガーデニング業者が多数登録しています。
造園系庭づくりであれば、庭木の新規植栽や植替えに伴う移植や土の入れ替え、防草シートや砂利敷きなどの雑草対策、庭石の設置や不要な庭石の撤去、天然芝の芝張りはもちろん、1年を通して庭を彩る流行りの人工芝まで、造園領域の庭作りを、造園系庭の手入れであれば、庭木の剪定や伐採・抜根、樹木の消毒などの庭木の手入れはもちろん、草刈りや防草シート、砂利敷きなどの雑草対策、その他芝刈りや雪国特有の作業である雪吊りや冬囲いまで、草や植木のお手入れを、あなたの要望を丁寧に聞きながら、安くて良いサービスを提案してくれますよ。
そこで、ここでは良い造園・ガーデニング業者を選ぶための方法を4つ紹介します。
01.造園・ガーデニング業者の種類から選ぶ
造園・ガーデニングに対応する業者は大きく分けると以下の6つに分けることができます。
それぞれメリット・デメリットがあるため、自身の目的にあった業者を選びましょう。
02.自宅から近い造園・ガーデニング業者を選ぶ
良さそうな造園・ガーデニング業者が複数見つかってしまった場合には、どちらのほうが作業現場に近いかで選ぶと良いでしょう。
人手不足の今、造園・ガーデニング業者さんも同時に様々なお客様の対応をしている場合があって日々忙しいため、遠い場所だと、施工中の緊急時や完成後のアフターフォローなど、中々すぐに駆け付けることは難しいことがほとんどですが、近場であれば、たまたまその付近にいるとか、工事の帰り道に伺うなど、比較的臨機応変に対応してもらえる確率が高まります。
そのため、できるだけ自宅に近い業者を選んでおくと安心です。
また、造園業界では植物を相手にするため、植物が良く成長し変化を起こす時期は一緒で、お客様の要望時期もだいたい決まった時期に集中します。そのため、繁忙期は非常に多忙となってしまうため、臨機応変に動くことが困難となる業者が多いためです。
03.保証やアフターサービスが充実している業者を選ぶ
造園・ガーデニングを業者に依頼する場合において気をつけておきたいことが、工事中の事故における損害保険への加入、枯れ保証や商品保証の有無、そしてアフターサービスが充実しているかどうかが意外と重要です。
損害保険に入っていれば、万が一、工事部分やその他の部分で事故が起きてしまった場合にも安心ですし、施工後に庭木が枯れてしまった際には枯れ保証や商品保証が付いていると安心です。
念のため、ご契約前に保証やアフターサービスはどうなのか業者に確認しておきましょう。通常、新規で植える場合の枯れ保証は半年から1年が相場です。ただし、移植や手入れの場合の枯れ保証は付かない業者が多い傾向です。
04.口コミや評価で業者を選ぶ
造園・ガーデニング業者が信頼できる業者かどうかを判断する一つの基準として、口コミや評価点などがあります。
事業者のホームページやレビューサイトを参考にして、どのような評価がされているのかチェックしておきましょう。
お庭の達人では、★評価に加え、お庭の達人のキャラクターや級、段位、本部認定のガーデナーなのかで評価が分かるようになっています。
当然ながら高評価が多い業者は信頼できる可能性が高いですが、お客様の要望によっては単純に評価点だけで選ぶと、専門違いということもあり得ますし、特に気をつけておきたいのが低い評価の口コミです。
その業者の専門性は何なのかということと、低い評価はどんな経緯だったのかを事前に把握しておくと、トラブルを未然に防ぐことができます。
まずは何社のお庭の達人(造園業者・庭師さん)がマッチングできるか簡単チェック!!
お庭の達人たちの紹介
造園・ガーデニングの費用相場

造園・ガーデニングを業者に依頼するといったいどの程度の費用が発生するのでしょうか?
造園・ガーデニングの費用は、庭木の本数だったり、作業対象の敷地の広さや行うサービスにより、大幅に変わります。
例えば、ガーデニングや庭づくりの場合、狭い敷地面積より広い敷地の方が、より多くの材料とそれを作る手間が多くかかります。そのため、面積に応じて費用が嵩みます。
他にも庭木を植える場合、過去の施工事例の現場と全く同じ敷地面積でも、そこに何本植えるのか、どんなサイズの、どんな種類の庭木を植えるのか・・・庭木は種類やサイズにより金額が違うため、お客様のご希望により、金額は大幅に上下します。
防草シートや砂利敷き、人工芝にしても、施工面積はどの程度か、砂利や人工芝の種類は何を使用するのか、現在の地盤の状態をどうなっているのかにより、金額は変わります。
そのため、概算の相場を出すことは非常に難しいことです。
一方、剪定や草刈りなど庭の手入れの場合は、作業したい庭木の本数やその庭木の高さとボリュームにより費用が変わりますし、草刈りの場合は面積がどの程度あるのか、草丈はどの程度あるのかで、作業の手間もごみの量も変わるため、費用も変わってきます。
つまり、造園・ガーデニングの見積をするには、お客様にヒアリングして、時には現在の状態を確認するために現場調査をしないと費用が出せないということになります。
そういう意味では、造園・ガーデニングには概算の費用相場という概念すらあまりないのですが、ただ、敷地面積がはっきりしていたり、木の本数や高さなどが明確になっていれば、おおよその費用相場はあります。
以下に解説しますので一緒に見ていきましょう。
庭の手入れ
庭の手入れとは、庭木の剪定や消毒、枯れた又は不要になった樹木の伐採、芝生の芝刈りや草刈り、除草剤散布などを指します。作業の種類としておおまかに分けると10種類ほどのサービス内容があります。
場所も庭だけでなく商業施設の緑地帯から空き家、空き地、駐車場などを管理維持します。ここではそれら1つ1つの相場を見ていきましょう。

庭木剪定の相場
植木屋・庭木剪定業者の料金体系は2パターンあり、人工(にんく)と言われる1人1日作業して○○円などという、いわば日給制のような場合と、剪定する庭木の高さや本数等に応じて料金がある程度決まっている単価制があります。
人工の場合は、作業の難易度によって庭師さん1人1日あたり2万円~4万円ほど、単価制の場合は庭木の高さや種類に応じて1本あたり1,000円〜3万円と幅があります。
木は同じ高さでも、ボリュームが1本1本違うので単価に幅があります。
さらに技術力が問われる松の剪定などのように、非常に手間と時間がかかる作業の場合は費用も高くなる傾向です。
どちらの料金の出し方にもメリットデメリットがあり、どちらが安いのかと言われると場合によるとしか言えません。
例えば人工の場合、まだ技術的にも経験的にも浅く作業も遅い庭師やその社員が作業を行ったとしても、それはそれで1人分となるためです。プロの庭師なら4時間で終わるところ、倍の8時間かかるということも経験が浅い方であればざらにあり得ます。
一方で単価制の場合は、多くの本数がある場合において、業者によっては割高になる場合もあります。そのため、どちらが良いのかは一概に言えません。
ただ、人工の場合は結局最終的に何人かかって何人工分の費用を払わなければいけないのかは、作業が終わらなければわからないという不安要素を抱えて依頼することになる場合もあるため、単価制で見積りをしてくれる業者が安心かもしれませんね。
また、こういった作業費用の他にも、切った枝葉の清掃費やその処分費が別途かかる場合があります。
では、庭木剪定の費用相場はどの程度でしょうか?ここでは、単価制における樹木の高さ別の相場をお伝えします。
相場を理解し、値段が安すぎる業者には注意しましょう!相場より安い植木屋に頼んでトラブルになることがあるからです。
実際、安い植木屋に依頼して花が咲かなくなった、実がならない、枯れたといったトラブルや、後から別途請求されたというトラブルが多く発生しています。
| 樹木の種類(松やマキ除く) | 庭木のサイズ | 庭木剪定前の料金相場(ゴミ処分費別) |
|---|---|---|
| 低木 | 高さ0〜1m | 500〜2,000円/1本あたり |
| 中木 | 高さ1〜3m | 2,000〜6,000円/1本あたり |
| 中高木 | 高さ3〜5m | 5,000〜15,000円/1本あたり |
| 高木 | 高さ5〜7m | 10,000〜30,000円/1本あたり |
| 大木 | 高さ7m以上 | 別途見積 |

生垣・植込み刈込剪定の相場
生垣や植込みの刈込剪定は、刈込バサミや電動のトリマーを利用して刈り込みますが、それぞれの刈込剪定の費用の決まり方は、生垣の場合は生垣自体の高さと距離に応じて、植込みの場合は面積に応じて変動します。
また、切った枝葉の清掃費やその処分費が別途かかる場合があります。
では、生垣や植込みの刈込剪定の費用相場はどの程度でしょうか?樹木の高さ別の相場をお伝えします。
相場を理解し、値段が安すぎる業者には注意しましょう!相場より安い植木屋に頼んでトラブルになることがあるからです。
実際、安い植木屋に依頼して花が咲かなくなった、実がならない、枯れた、といったトラブルが多く発生しています。
| 生垣のサイズ | 生垣刈込剪定の料金相場(ゴミ処分費別) |
|---|---|
| 高さ0〜1m | 500〜1,000円/1mあたり |
| 高さ1〜2m | 1,000〜2,000円/1mあたり |
| 高さ2〜3m | 2,000〜3,500円/1mあたり |
| 高さ3m以上 | 別途見積り |
| 植込みの状態 | 植込み選定の料金相場(ゴミ処分費別) |
| 1種類の植込み | 500〜1,500円/1m2あたり |
| 多種混植の植込み | 別途見積 |

消毒の相場
毛虫や害虫、病気から庭木や生垣などを守るためには消毒は欠かせません。どんな木でも、毛虫から被害を受ける場合もありますし、ダニやカビから病気になる可能性もあります。
ある日突然、枯れてしまったということがないように、1年に2回、最低でも1回は行うようにしましょう。
では、庭木の消毒の費用はどの程度かかるのでしょうか。
消毒を業者に依頼すると、作業にかかる人件費と農薬代、そして散布機等の機械代、燃料代が掛かります。
木の本数や広さによってそれら原価が変わる為、お客様に発生する費用も変わります。そのため、ここではおおよそ木の本数を目安に消毒の相場を下記に示します。
相場を理解し、値段が安すぎる業者には注意しましょう!相場より安い植木屋に頼んでトラブルになることがあるからです。
実際、安い植木屋に依頼して消毒をして枯れてしまった、消毒したのに虫がいなくならない、病気が改善しないなどといったトラブルが多く発生しています。
| 樹木の高さ | 庭木の本数 | 庭木剪消毒の相場(各種諸経費含む) |
|---|---|---|
| 高さ3m未満 | 1〜10本程度 | 8,000〜20,000円 |
| 高さ3〜5m | 1〜10本程度 | 1,000〜25,000円 |
| 高さ5〜7m | 1〜10本程度 | 12,000〜30,000円 |
| 高さ7m以上 | 1〜10本程度 | 別途見積 |

伐採の相場
庭木を定期的に剪定せず放置してしまうと、非常に大きく育ちすぎてしまい、枝葉がお隣さんの敷地に越境してご近所問題を引き起こしてしまったり、強風や台風の際に倒木したり、傾いたりしてしまうことがあります。
そうなると非常に危険な為、伐採を検討しなければなりません。大きければ大きいほど、一般の方で行うことは非常に危険な為、植木屋さんや造園屋さんに依頼することになりますが、では、伐採を業者に依頼しようと思うと一体いくらぐらいの相場となるのでしょうか?
伐採の相場は、その木自体の高さに加え幹の太さにより木自体の重量が変わる為、危険性や難易度が変わります。
また、切る枝を真下に落とせるのか、屋根や構造物があると壊してしまうため、クレーン車で吊りながらなど、養生をしながら行う必要があるのかなど、作業の工法によっても料金が変わります。
そのため、相場はあくまで概算となる為、正式な見積には必ず現場調査が必要となることを覚えておきましょう。
ごみの処分費も、その木自体のボリュームによりますので、概算は難しいのが実情です。(極端な話、木は成長してボリュームが年々増える為、同じ場所に植わっている同じ木でも、今年より来年の方が処分費が高くなります)
| 庭木の高さ | 幹の太さ(直径) | 伐採の料金相場(ごみ処分費別) |
|---|---|---|
| 高さ3m未満 | 直径15cm未満 | 3,000〜10,000円/1本あたり |
| 直径15cm未満 | 10,000〜25,000円/1本あたり | |
| 高さ3〜5m | 直径15cm未満 | 6,000〜25,000円/1本あたり |
| 直径15cm未満 | 25,000〜55,000円/1本あたり | |
| 高さ5〜7m | 直径15cm未満 | 15,000〜50,000円/1本あたり |
| 直径15cm未満 | 50,000〜80,000円/1本あたり | |
| 高さ7m以上 | − | 別途見積 |

抜根の相場
伐採後、切り株になった根を抜く作業を抜根(伐根)と言います。
樹木の根は、台風などの強風等に簡単に倒れてしまわないよう、地中で根を張り巡らしています。おおよそ、枝の長さ、広がりと同じほどの根が地中に広がっていると考えましょう。
そんな根を抜く作業は、幹が細い樹木であれば人力作業で抜根が可能ですが、大体の場合はバックホウなどの重機が必要となります。
そのため、費用の前にそもそもその木を抜根可能なのかどうかを判断しましょう。
近くにコンクリートがある場合や、塀などがある場合ではそもそも掘ることすらできませんし、また、そこには水道や電気、ガスの管が地中を走っている場合には、掘ること自体危険です。
例え掘ることが出来たとしても、そこまで重機が入れるのかどうかで作業の可否が変わります。
業者に見積りを依頼すれば、抜根が可能かどうかの判断を含めてお見積りをしてくれます。業者に依頼する場合の気になる相場を下記に示しますが、あくまで概算の相場です。
抜きたい根の植わっている場所、作業の方法により大幅に料金も変わるということを覚えておきましょう。
| 根元の幹の太さ(根元周り) | 銃器作業の抜根(伐根)の料金相場(重機費・ごみ処分費別) |
|---|---|
| 根元周り30cm未満 | 5,000〜15,000円/1株あたり |
| 根元周り30〜60cm | 10,000〜25,000円/1株あたり |
| 根元周り60〜90cm | 15,000〜35,000円/1株あたり |
| 根元周り90cm以上 | 別途見積 |

ツリークライミング(特殊伐採)の相場
ツリークライミング(特殊伐採)とは、クレーン車等が入れない場所や非常に狭い場所での大木(おおよそ7m以上)の伐採に対する技術や工法の事で、庭師の中でも限られた講習を受け、その卓越した技術を持っている職人のみができる非常に難易度の高い作業です。その庭師たちを、空師ともいいます。
10m以上の木に自ら登り、ロープ等を使用して切断した枝や幹を安全に下ろしていく作業で、作業者が常に命の危険を感じながら作業するのはもちろん、周辺の家屋や電線、通行車両等への影響のリスクが伴います。
つまり、作業自体非常に危険な作業となる為、講習を受講して資格を取得した空師のみ可能な作業でしょう。
そのため、自ずと見積額も高くなりがちです。
さて、相場に関してですが、そもそも特殊伐採自体、特殊な環境に生えている木を伐採することですから、その木のボリュームや作業環境等を鑑みて作業方法が決まるため、相場自体ご紹介することは困難です。見てみないと分からないとしか言いようがありません・・・。
しかし、特殊伐採の見積の際に一般的に用いられる計算式がありますので、よろしければ参考にしてみてください。
| ツリークライミング(特殊伐採)費用の一般的な計算式(重機費・ゴミ処分費別) | |
|---|---|
| 伐採する木の高さ(m)x木の本数x5,000円x危険係数(1~5) ※ただし、別途木のボリュームに応じた枝葉幹等の処分費用及び重機費用がかかります。 |
|
| Q&A | |
| 木の高さの目安は? | 2階建ての一般住宅の屋根上までで8m前後になります。 |
| 一般的な電柱で12mほどになります。 | |
| 伐採の危険係数とは? | 危険度に応じて危険係数1~5が定められています。 |
| 危険係数の条件 | |
| 危険係数゠1 | 周囲に障害物がなく、木を切り倒すための十分なスペースがある場合 |
| 危険係数゠2 | 重機が近づくことができるかつ、家屋や電線等の障害物があるものの、ある程度のスペースが確保でき、枝葉の切り落としがコントロールがしやすい場合 |
| 危険係数゠3 | 重機が近づくことができないが、家屋や電線等の障害物があるものの、ある程度のスペースが確保でき、枝葉の切り落としがコントロールがしやすい場合 |
| 危険係数゠4 | 電線とごく近く感電の恐れがある、民家や道路などに張り出していて枝の落下に細心の注意が必要など、周囲のスペースに制限がある場合 |
| 危険係数゠5 | 法面や民家の屋根の上など、不安定な位置に倒れ掛かっている、木自体が枯れていて折れやすい、枝の張り出しが非常に大きい、その他作業中に様々な危険がある場合 |

冬囲い・雪吊りの相場
秋の終わりごろになると雪国の地域で多く見られる風物詩として、冬囲い・雪吊りが見られます。
これは、冬の雪に備えて行う作業で、枝に積もる雪の重みで折れてしまわないように保護するための庭木保護目的で行われるものです。
冬囲い・雪吊りの種類として、縄巻き・竹囲い・生垣(植込み)竹囲い・雪吊り・幹吊り・ムシロ掛けなどがあり、庭木の大きさ、庭木の種類により、あとはご予算に応じて使い分けます。
雪囲いで全国的に有名なのは兼六園ですが、兼六園の場合は「りんご吊り」と呼ばれており、非常に壮大な風景です。
では、冬囲い・雪吊りを業者に依頼する場合の相場はどの程度の費用が発生するのでしょうか?
各種相場と共にお伝えいたします。ただし、枝張りなど木のボリュームによって費用は変動いたしますので、下記相場の限りではございません。
また、別途春ごろの撤去時には撤去作業費用と処分費が発生いたします。
| 冬囲い・雪吊りの種類 | 庭木のサイズ | 庭木剪定の料金相場(ごみ処分費別) |
|---|---|---|
| 縄巻き・ムシロ掛け | 高さ4m未満 | 1,500〜7,000円/1本あたり |
| 竹囲い | 高さ4m未満 | 2,000〜8,000円/1本あたり |
| 幹吊り | 高さ5m未満 | 3,000〜10,000円/1本あたり |
| 雪吊り | 高さ5m未満 | 5,000〜15,000円/1本あたり |

草刈り・草取り・除草剤の相場
雑草のメンテナンスには、人力作業で草を抜く『草むしり』、肩掛け式草刈り機を使用した『草刈り』、広い面積の場合にはハンマーナイフやロータリーモアといった手押し式や乗用式の草刈り機を使用した『草刈り』があり、その他草の根まで枯らす『除草剤散布』があります。
それぞれ、面積や作業環境に応じて使い分けますが、大きな機械を利用すればするほど生産性が高まり、1日で作業できる範囲が変わります。
そのため、草刈り単価も生産性に応じて変わります。
草刈りを業者に依頼する場合、どの程度の相場でどの程度の費用がかかるのか下記の表にまとめますので参考にしてください。
なお、草が生えている密度や草丈(草の高さ)に応じて同じ作業場所でも費用が変わりますし、その処分費も変わります。
| 草刈り・草取りの種類 | 草のサイズ | 草刈り・草取りの料金相場(ごみ処分費別) |
|---|---|---|
| 草取り(草むしり) | − | 1,000〜2,000円/1m2あたり |
| 草刈り(機械刈り) | 草丈1m未満 | 200〜600円/1m2あたり |
| 草刈り(機械刈り) | 草丈1〜1.5m | 400〜700円/1m2あたり |
| 草刈り(機械刈り) | 草丈1.5m以上 | 500〜1,000円/1m2あたり |

芝刈り・芝のメンテナンスの相場
芝のメンテナンスには、大きく分けて3つあります。
1つ目は、芝刈りです。肩掛け式芝刈り機を使用した『芝刈り』、広い面積の場合にはロータリーモアといった手押し式や乗用式の芝刈り機を使用した『芝刈り』があります。
それぞれ、面積や作業環境に応じて使い分けますが、大きな機械を利用すればするほど生産性が高まり、1日で作業できる範囲が変わります。
そのため、芝刈り単価も生産性に応じて変わります。
2つ目に芝のエアレーションです。エアレーションは芝の発育促進のために行う作業で、芝に専用具を使用して穴をあけ、通気性を良くしていきます。
3つ目に芝の目土と施肥です。エアレーションとセットで行うことが普通ですが、エアレーションで空けた穴に土を埋め、根が張るように促し、さらに肥料を蒔くことで発育を補助します。
それら作業を業者に依頼する場合、どの程度の相場でどの程度の費用がかかるのか下記の表にまとめますので参考にしてください。
| 芝刈り・芝のメンテナンスの種類 | 芝刈りの料金相場(ごみ処分費別) |
|---|---|
| 芝刈り | 250〜500円/1m2あたり |
| エアレーション・目土 | 500〜2,000円/1m2あたり |
造園・庭づくり
造園・庭づくりとは、人工的な構造物を扱う外構ではなく、庭木や芝などの植物系の工事や、自然物の庭石や砂利などの工事を指しますが、種類としておおまかに分けると10種類ほどのサービス内容があります。外構と違い、造園の知識や技術が必要な作業です。それら1つ1つの相場を見ていきましょう。

庭木植栽の相場
新築時の庭づくりとして庭木を植栽することがありますが、その目的は様々あります。
1つ目は観賞目的としてや温かみを感じられる庭にすること。外構だけの構造物だけだと、殺風景に見えてしまいますが、そこに自然豊かなシンボルツリーが入ることで、温かみが感じられ、爽やかな庭に彩ることができます。
2つ目は目隠しです。実際に住宅に住んでみると、思いのほかお隣さんや通行人から見られることが発覚します。その目線を隠すために庭木で目隠しをします。
では、植栽工事の費用相場はどの程度でしょうか?(DIYで行うような小さな苗木の植栽の場合は除きます。)
本数や樹木の種類によるので一概に言えませんが、最初から完成された大サイズ・中サイズの庭木を何本か植える場合は、およそ外構工事費用の10%ほどと言われています。
5%だとこれから成長を楽しむような、まだ苗木の小さな庭木の植栽となり、流行りのアオダモなど雑木風の自然あふれる庭木を何本も植える場合には、およそ外構工事費用の20~30%ほどとなります。
ここでは、外構工事費用が100~200万円レベルの敷地面積の場合における、一般的な流行りの樹木代と植込み費用含む植栽工事の相場を、本数別でお伝えします。
| 植栽する本数 | 庭木のサイズ | 庭木植栽の料金相場(植込み費・樹木費含む) |
|---|---|---|
| 2〜4本 | 高さ1.5〜3m | 10万〜20万円 |
| 5〜7本 | 高さ1.5〜3m | 15万〜30万円 |
| 8〜10本 | 高さ1.5〜3m | 20万〜40万円 |

生垣・植込植栽の相場
生垣や植込みの植栽はそれぞれ目的が違うと思いますが、生垣は主に目隠し目的で使用され、植込みの植栽は主に観賞目的で利用されます。
それぞれの費用の決まり方は、生垣の場合は距離に応じて、植込みの場合は面積に応じて低木や下草の本数が決まりますが、例えば、生垣の場合は延長1m当りに何本植えるのかによっても樹木の本数は変わりますし、植込みの場合も面積1㎡当りに何本植えるのかで本数が変わり、費用も変動します。
ここでは、生垣で一般的に植える密度である1m当り3本として、高さ別に相場を記載し、植込みの場合は一般的な相場をお伝えいたします。
| 距離10mの生垣植栽の場合 | ||
|---|---|---|
| 1m当たり植栽する本数 | 生垣樹木のサイズ | 生垣植栽の相場(植込み費・樹木費含む) |
| 2〜3本 | 高さ0.5m | 5万〜10万円 |
| 2〜3本 | 高さ1m | 8万〜13万円 |
| 2〜3本 | 高さ1.5m | 10万〜15万円 |
| 面積5m2の植込み植栽の場合 | ||
| 1m当たり植栽する本数 | 生垣樹木のサイズ | 生垣植栽の相場(植込み費・樹木費含む) |
| 7〜10本 | 5種類程度 | 5万〜8万円 |

移植の相場
家や庭の建て替えやリフォームに伴う移植、引っ越しに伴う移植など、移植を行うのは植えてから何十年と長年経った木がほとんどかと思います。
そんな数十年同じ場所に植わっていた庭木は、すでに大きく育ち、幹も太くなっているがために、植木屋さんの技術力に加え、何百kgもの重さの庭木を移動させる重機も必要不可欠です。
また、抜根に伴う撤去とは違い、生かすために根を掘り起こされる移植は、様々な造園技術と経験が必要な、造園業の中でも最も技術力が試される作業です。そのため、自ずと料金はかさみます。
よく移植を業者に依頼すると、『既存の庭木を撤去して新たに植木屋さんで同じ庭木を買って植えたほうが安いよ』と言われたことがある方も多いかと思いますが、実際にその通りで、撤去して新たに買って植えたほうが安くなるのが現実です。
しかしそれでも、記念樹だったり、思い出の深い庭木だったりすると移植する場合があります。
そこでここでは、移植に伴う費用の相場をお伝えいたします。ただし、重機が入れる場所なのか、クレーン車が届く場所なのかどうかで料金は大幅に変わるのでご注意ください。
| 樹木の高さ | 幹の太さ | 移植の相場(重機費含む) |
|---|---|---|
| 高さ2〜3m | 幹の直径3cm(幹周り10cm) | 2万〜7万円 |
| 高さ2〜3m | 幹の直径5cm(幹周り15cm) | 5万〜10万円 |
| 高さ2〜3m | 幹の直径10cm(幹周り30cm) | 7万〜12万円 |
| 高さ3〜4m | 幹の直径5cm(幹周り15cm) | 7万〜12万円 |
| 高さ3〜4m | 幹の直径10cm(幹周り30cm) | 10万〜15万円 |

木の立て起こし・支柱更新の相場
木の立て起こしや支柱更新は台風前の時期に非常に多くなるサービスの一つですが、記載の通り、台風等で倒れた樹木や傾いた樹木に行うサービスです。
一度傾いた樹木は根が切れてしまっておりますので、立て起こしたところで枯れてしまうことが多々あり、さらに幹が太く重量がある木だと立て起こすのは非常に難しい作業で、最悪の場合は伐採せざるを得ないことが多々あります。
多少傾いた樹木であれば、起こし直すことができる場合がありますが、たいていの場合は人力では起こせないので、クレーン車等が必要です。
立て起こしができた場合でも一旦根が切れてしまっている状態のため、再度倒れないように木を支えるため、支柱を更新したり、新たに支柱を設置したりします。
そんな、一般的な木の立て起こし・支柱更新の料金相場をお伝えいたしますので参考にしてください。なお、クレーン車などの重機費用は別途となります。
| 樹木の高さ | 木の立て起こし・支柱更新の相場(重機費別) |
|---|---|
| 高さ1〜3m | 1万〜5万円 |
| 高さ3〜5m | 3万〜10万円 |

芝張りの相場
庭の地面に行う造園工事は芝張り・砂利敷き・人工芝の3つがメインですが、一番利用される工事で一番安い方法が天然芝の芝張り作業です。
人工芝も最近人気ですが、やはり人工的で年中代わり映えが無いため、冬は違和感が多少あります。その点、天然芝は季節通り冬には茶色く枯れ、春には爽やかな緑に変わり、四季を通して様々な変化を楽しませてくれるため、自然な感じで人気があります。
そんな天然芝には様々な種類がございますが、種類別で芝張り費用の相場をお伝えいたしますので参考にしてください。なお、施工面積が余りに少数の場合は単価は割高になるためこの限りではありません。
また、張る箇所の地面の下地の状態(石が多い、地面がそもそも低い、既存の天然芝を剥がす必要があるなど)により、芝張り費用とは別で芝を張る以前の造成工事が必要になる場合がありますのでご注意ください。
| 芝生の種類 | 1m2当たりの相場(芝生費・芝張り費・目土費含む) |
|---|---|
| 高麗芝 | 2,000〜4,000円 |
| TM19 | 3,000〜5,000円 |
| 西洋芝 | 2,000〜4,000円 |

土入れ・残土処分の相場
新築時に庭を作る際や既存の花壇の土を入れ替える際など、必ず発生するのが土が足りない場合の土入れ作業または、反対に土が多い場合の掘削及び残土処分作業です。
基本的に土を触る土木工事は重機作業となり、重機が入っていけないような狭い場所の場合は、人力作業で土入れや土の掘削を行う必要があり、非常に生産性が悪い作業になることから、思った以上に見積も割高になります。
そのため、土を触る工事をご希望の場合は、重機が入れるのか入れないのかをよく確認しましょう。
ここでは、重機作業が前提とした土入れ・掘削・残土処分の費用相場をお伝えいたします。ただし、残土を敷地外処分の場合は、地域ごとに相場が変わる処分費に加え、処分場までの距離により費用が変わる場合があります。また、施工面積が余りに少数の場合は単価は割高になるためこの限りではありません。
| 作業の種類 | 1m3(立米)当たりの相場 |
|---|---|
| 土入れ(土壌改良) | 10,000〜30,000円 |
| 既存土掘削 | 3,000〜6,000円 |
| 残土処分(敷地内敷き均し) | 3,000〜6,000円 |
| 残土処分(敷地外処分) | 6,000〜10,000円 |

雑草対策工事(防草シート・砂利敷き)の相場
雑草魂という言葉があるほど、雑草は抜いても抜いてもすぐに生えてくる非常に根性のある厄介な植物ですが、そんな雑草を完全に遮断する方法はほぼありません。
コンクリートを打っても、キワの隙間や割れたヒビから生える場合があります。
しかし、雑草を生えにくくする方法は様々あります。それは、コンクリートを打つ方法や、レンガや石を張る方法、固まる土と言うセメントが混ざった真砂土を敷き詰める方法、人工芝を敷く方法、そして防草シートを敷く方法です。
その中でも、一番安い方法がこの防草シートを敷く方法です。防草シートだけでは殺風景で見た目は良くないため、その上に砂利を敷くのが一般的です。
ここでは、防草シート及び砂利敷きの費用相場をお伝えいたします。ただし、防草シートや砂利は見た目の違いや耐久性などの違いにより、種類も値段もピンキリです。
そのため、おおよその金額感とご理解ください。なお、施工面積が余りに少数の場合は単価は割高になるためこの限りではありません。
| 作業の種類 | 1m2当りの相場(除草シートまたは砂利費・作業費含む) |
|---|---|
| 除草シート敷設 | 1,500〜3,000円 |
| 砕石敷き均し | 1,500〜3,000円 |
| 砂利敷き均し | 2,000〜5,000円 |

人工芝の相場
雑草を生えにくくする方法の一つである人工芝。年間を通して爽やかな緑を庭に与えくれる人気の庭の地面工事です。
ドッグランとしてや子供が怪我しにくくなるような遊び場づくりとして非常に人気です。
ただし、天然芝に比べると施工費用は1㎡当り3~4倍するため、特に人工芝にこだわりが無い場合は天然芝をお勧めいたします。
DIYで行う場合は、人工芝を張る前の地盤の状態に注意しましょう。地盤が凸凹だと人工芝を張った仕上りも凸凹になります。人工芝敷きは地盤が命といっても過言ではないくらい地盤づくりが非常に大切です。
ここでは、防草シート及び人工芝敷きの費用相場をお伝えいたします。ただし、防草シートや人工芝は見た目の違いや耐久性などの違いにより、種類も値段もピンキリです。
そのため、おおよその金額感とご理解ください。なお、施工面積が余りに少数の場合は単価は割高になったり、人工芝を張る前の地盤づくりが別途必要な場合はこの限りではありません。
| 作業の種類 | 1m2当りの相場(防草シート及び人工芝費・作業費含む) |
|---|---|
| 通常レベル人工芝 | 5,000〜10,000円 |
| 中級レベル人工芝 | 8,000〜13,000円 |
| 高級レベル人工芝 | 10,000〜15,000円 |

造園・石工事の相場
最近では、昔ながらの大きな庭石や景石、灯籠を撤去する需要が多い反面、割栗石という10~20cm程度の石を花壇内や門塀の周りに設置するロックガーデンデザインが流行っています。
庭石の撤去の場合、非常に大きな石であることから人力で運び出すことは難しく、クレーン車などの重機が必要となり、庭石の撤去及び処分で見積りを取ってみると、思いのほか高くて断念するというお客様が非常に多くいらっしゃいます。
その反面、割栗石であればオシャレな上に、例え庭のリフォームを将来することになっても、小さい石ですので人力で運び出して処分するということも容易です。
そんな”石”に関して、各種石工事の費用相場はどの程度なのか見ていきましょう。
ただし、石は人工的なものではなく自然の鉱石です。そのため、石の種類・産地により料金はピンキリですのでご注意ください。ここでは、一般的に良く流通する石を想定した費用相場をお伝えいたします。
| 作業の種類 | 1個当りの相場(石費・作業費含むがサイズによる) |
|---|---|
| 庭石設置 | 30,000〜60,000円 |
| 庭石撤去・処分 | 10,000〜100,000円 |
| 作業の種類 | 1m2当りの相場(石費・作業費含む) |
| 割栗石(国産) | 8,000〜15,000円 |
| 割栗石(海外産) | 15,000〜30,000円 |
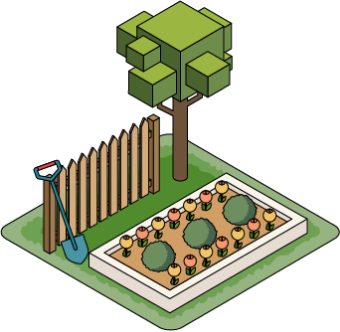
その他造園工事の相場
その他、造園系庭づくりには、工場や高層ビル、ショッピングモールなどに作られる空中庭園など、屋上緑化や壁面緑化、そして、法人様事務所や一般個人の住宅でも室内に設置される観葉植物があります。
都心のビル群では、屋上緑化や壁面緑化があることで、ヒートアイランド現象の緩和や施設の省エネ向上、大気の浄化、都市景観の向上などをもたらしてくれることから、重宝されています。
そんな屋上緑化や壁面緑化の費用相場はどの程度なのでしょうか?以下にまとめますが、費用はあくまでも目安です。水やり設備や資材の搬入方法によるクレーン車使用費等は別途発生します。
屋上の広さや壁面の広さ、立地、設備の品質、樹木や芝生の有無などによって金額は大きく変わるため、見積を取ることが大切です。
| 屋上緑化の方法 | 1m2当りの相場(屋上緑化システム及び植物費・作業費含む) |
|---|---|
| トレー式セダム緑化 | 10,000〜20,000円 |
| 天然芝張り | 15,000〜25,000円 |
| 庭園づくり・緑化 | 100,000〜500,000円 |
| 壁面緑化の方法 | 1m2当りの相場(壁面緑化システム及び植物費・作業費含む) |
| 壁面緑化 | 50,000〜200,000円 |



地域から探す
まずは何社のお庭の達人(造園業者・庭師さん)がマッチングできるか簡単チェック!!
造園・ガーデニングはDIYできる?

造園・ガーデニングを業者に頼まず、自分でやってみたいと考えている人もいますよね。草むしりや防草シート敷きなどの簡易的な工事なら比較的簡単なので、自分でやってみてもよさそうです。
しかし、草丈の高い草刈りや庭木の剪定など、切ったごみの処分は一般の方では中々難しく、しかも変な切り方してしまったら元に戻りません。
他にも防草シート敷きや人工芝の地面の基礎作りをDIYでやるのは非常に難易度も高いですし、移植・植え替えなどに至っては、技術的な面や重機など機械や道具の有無で、工事の難易度が変わります。
そういう意味で、DIYでの造園・ガーデニングには「良さ」と「悪さ」の両方が存在します。
そのため、ここでは造園・ガーデニングのDIYのメリットやデメリットなどについて解説します。
造園・ガーデニングDIYのメリット
DIYで造園・ガーデニングを進めたときのメリットについてまずは見ていきましょう。
費用面の他にもさまざまなメリットがあります。
造園・ガーデニングDIYのデメリット
DIYで造園・ガーデニングを行う際のデメリットについて見ていきましょう。
費用面などのメリットばかりに捉われてしまうと、大事な品質や安全性という面がデメリットになってしまいかねません。
お庭の達人に関してのQ&A
庭木の剪定はどのように料金が決まるの?
料金設定には2種類あり、1時間で〇円と時間で設定しているところと、木の高さと本数で〇円と設定している事業者があります。依頼したい範囲と、3mを超える高い木があるかどうかなどを考えて事業者を選ぶことをおすすめします。
1本だけお願いしたいという依頼も大丈夫?
1本だけ植木の剪定をお願いしたいという依頼ももちろん出来ます。ただし、出張費や最低受注金額を設けている事業者がほとんどです。作業量が少ない場合はどのような見積もりになるかを確認しましょう。
庭木を剪定するとどんな効果があるの?
お庭の景観が美しくなることはもちろんですが、葉の日当たり・風通しを良くすることによって病気や害虫から庭木を守る効果があります。
造園・ガーデニングに関する記事
造園・ガーデニングに関するさまざまなお役立ち記事を紹介しています。

タイトル
ああああああああああああああああああああああああああああああ....

タイトル
ああああああああああああああああああああああああああああああ....

タイトル
ああああああああああああああああああああああああああああああ....

タイトル
ああああああああああああああああああああああああああああああ....

タイトル
ああああああああああああああああああああああああああああああ....

タイトル
ああああああああああああああああああああああああああああああ....
まずは何社のお庭の達人(造園業者・庭師さん)がマッチングできるか簡単チェック!!



































回答が入ります。回答が入ります。回答が入ります。回答が入ります。回答が入ります。回答が入ります。回答が入ります。回答が入ります。回答が入ります。